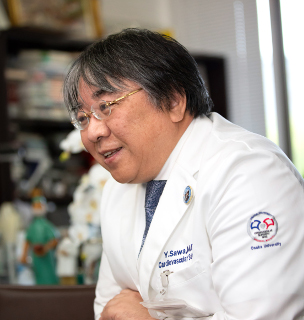- 2019.05.20
- コラム
CAR-T細胞療法:がんの殺し屋の力を結集させる
ASCA Bulletin 22号では、山口大学医学部大学院医学系研究科免疫学教授の玉田 耕治先生を取材させていただきました。
がん免疫療法の新たな切り札として注目を集めているCAR-T(カーティ)細胞療法は、2018年にノーベル生理学・医学賞の対象となった免疫チェックポイント阻害薬に続く新しい治療法です。玉田先生はこのCAR-T細胞の先進的研究に取り組まれておられます。
ゲノム研究と免疫学から生まれたCAR-T細胞
がんに対する免疫療法は著しい発展を遂げています。近年では免疫チェックポイント阻害薬など高い有効性を示す治療法も登場し、いま大きく期待されている研究領域です。CAR-T細胞療法は、その免疫療法の中では細胞療法のひとつに大別されます。細胞療法は、がん細胞を攻撃するT細胞やNK細胞などの免疫細胞を直接体内に注入し、体の免疫機能を高める治療です。これまでの細胞療法は、患者さんから採取したT細胞などを増殖して体内に戻すという方法が主流でしたが、CAR-T細胞療法では、がんに対する免疫反応をより強力に誘導できるような仕組みを作り出していることが大きく違います。T細胞自体にもがんを攻撃の標的にできるものはあるのですが、その割合は非常に低いため、単にT細胞を増やしても思うような治療効果を得ることは困難でした。そこで、遺伝子の改変によってがんに対する特異性の高いT細胞だけを人工的に増やし、がんを効率よく攻撃させようというのがCAR-T細胞療法の発想です。
CAR-T細胞は、キメラ抗原受容体(chimeric antigen receptor:CAR)発現T細胞の頭文字を取って名付けられたものです。T細胞は、T細胞受容体(TCR)と呼ばれるタンパク質の複合体を細胞表面に発現しており、この部位が攻撃する標的を認識しています。CAR-T細胞ではこのTCRの代わりにCARを利用して腫瘍細胞の抗原を特異的に認識します。CARは細胞膜を貫く形で、主に3つのパーツから構成されています(図左)。まず細胞外にはscFv(single-chain variable fragment)と呼ばれる1本鎖抗体があり、この抗体がCD19など特定の腫瘍関連分子に結合する機能を有しています。そしてこの部分を細胞の中へとつなぐ細胞膜貫通ドメインを経て、細胞内にはT細胞を刺激するためのT細胞活性化シグナル伝達ドメインが作られています。現在のCARは第2あるいは第3世代が使用されており、細胞内ドメインが共刺激分子を含む2つ以上のユニットから構成されており、活性化シグナルの伝達効率を高める構造になっています。こうした仕組みによって、がんを見つけるとCARはその抗原に結合してT細胞を強力に活性化させ、腫瘍細胞を傷害することができます。
CAR-T細胞を作製するには、患者さんから採取した末梢血リンパ球にCAR遺伝子を導入します。遺伝子の組み換えには、レンチウイルスやレトロウイルスなどのウイルスベクターを用いた方法が一般的です。遺伝子導入によってCARを発現した細胞を体外で培養し増殖させた後、患者さんの体に静注で戻す、というのが通常のCAR-T細胞療法の流れです。
始まっているCAR-T細胞療法の臨床応用
B細胞系のがんに発現するCD19を標的としたCAR-T細胞を用いた臨床試験では、B細胞性急性リンパ芽球性白血病(ALL)に対して8割(1) 、非ホジキンリンパ腫に対して5割(2)を超える患者さんで完全寛解を示しました。この結果の驚くべき点は再発性・難治性の患者さん、すなわち他に治療法のない患者さんに対してこれだけの効果を示したことです。このような結果から、2017年以降米国、欧州で相次いでチサゲンレクルという薬剤として承認を受けています。日本でも2019年2月に行われた厚生労働省の審査を経て、3月27日に承認されました。
副作用としてはサイトカイン放出症候群(CRS)が最もよく知られており、治療を受けた患者さんの7割程度で起こります。これは文字通りT細胞の活動によって体内で放出されるサイトカインが急激に増加し、症状としては発熱や呼吸困難、血圧低下などがみられるのですが、抗IL-6受容体抗体の投与によってかなりコントロールできることがわかっています。
今後は、他の血液がんや一次治療での使用についても臨床試験でその有効性が明らかになっていくだろうと期待されています。慢性リンパ球性白血病(CLL)でも一定の効果はあると考えられていますし、多発性骨髄腫ではBCMAという別の抗原をターゲットにすることで治療効果が示されています(3)。一方で、このCAR-T細胞療法は、すべての患者さんに対して用いられる治療というわけでもないと考えています。すなわち、現在のがん治療はきわめて細分化されており、患者さんの状態やバイオマーカーの存在によってどの治療を行うかが決定されます。場合によってはCAR-T細胞療法よりも分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬、あるいは骨髄移植の方が適しているケースもあるはずですし、副作用がでやすい患者さんもいるかもしれません。こうした治療の最適化を今後の研究を通じて考えていく必要があります。例えばCD19 CAR-T細胞療法は当然ながらCD19を発現している患者さんに対して高い効果を発揮するのですが、中には再発する例があり、それらの一部ではがん細胞上のCD19発現が消失するという現象が起こることが知られています。この現象を遺伝子検査などによって予測できれば、治療法の決定や治療対象のセレクションにも役立つでしょう。
CAR-T細胞療法の進化と今後の展開
血液がんに対して非常に高い有効性を示したということで、今後は固形がんの治療への応用に期待がかかるのは当然の成り行きです。固形がんにどう効かせるかを考えたとき、問題となる点は主に2つあり、そのひとつが抗体の標的です。通常、CAR-T細胞がその表面に発現する1本鎖抗体は、ひとつの抗原をターゲッティングして認識します。先述のALLなどでは、CD19というひとつの標的だけで非常に高い効果を示すことができたのですが、固形がんは少し事情が異なります。例えば胃がんでは、がん細胞が持つマーカーは極めて多様であり、単一の抗原に特異的なCAR-T細胞ではすべてのがん細胞を標的にできないことが予想されます。では多数の抗原それぞれに対応したCAR-T細胞を作製すればよいのかというと、それは時間やコストの問題を考えると現実的ではありません。したがって、固形がんでCAR-T細胞療法に有効性を持たせるためには、単一のCAR-T細胞の反応から結果的に多様な腫瘍細胞を攻撃できるような仕組みを作ることが必要になります。もうひとつの問題は、細胞の送達性です。すなわち、血液中を循環するCAR-T細胞を腫瘍部位にピンポイントで届けなければいけないということです。白血病などの血液がんの場合は、CAR-T細胞が血液中にあればその時点で攻撃対象であるがん細胞を認識することができるのですが、固形がんの場合は、血管外にあるさまざまな臓器にCAR-T細胞を行き渡らせるための戦略が必要です。
この2つの課題を解決するために、私たちはリンパ球などの免疫細胞ががんの局所に集まってくるシステムを組み込んだCAR-T細胞の開発を目指しています。CAR-T細胞が固形がんにたどり着いたとき、わずかな数のCAR-T細胞では大きな腫瘍組織に勝ち目がありません。そこで、がんを発見したCAR-T細胞が仲間のT細胞や樹状細胞を呼び寄せるようにすれば、数の面でも抗原認識の多様性の面でも太刀打ちできるようになるのではということです。この仕組みには、ケモカインとサイトカインの性質を利用しています。ケモカインは細胞遊走因子であり、CCL19と呼ばれる分子をCAR-T細胞に産生させることで周囲の免疫細胞の遊走性をコントロールし、CAR-T細胞のもとに集まるよう促しています。さらに増殖を誘導するサイトカインIL-7も導入しておくことで、CAR-T細胞を増やし、さらに多くの免疫細胞を集めて増殖させることができるようになります。こうすることで、単独の標的を持つCAR-T細胞のみではなく、患者さんの体内に存在する、いわゆるポリクローナルな免疫細胞の集団を作り、協調してがんに立ち向かうことができます。私たちはこのCAR-T細胞を7×19 CAR-T細胞(Prime CAR-T細胞)と呼んでおり、固形がんモデルのマウスで高い治療効果があることを示してNature Biotechnology誌に発表しました(4)(図)。ヒトへの応用を目指して、現在ベンチャー企業や製薬企業と共同で研究開発を進めています。将来的には様々な固形がんや難治性のがんに対して有効なアプローチになることを期待しています。
図(左)従来型のCAR-T細胞によるがん治療。細胞外の抗体部分が腫瘍細胞表面の抗原を認識し結合する。(右)改良された7×19 CAR-T細胞(Prime Car-T細胞)を利用した治療。CAR-T細胞自身の働きに加え、CCL19によって周囲の免疫細胞を腫瘍細胞に誘導し、IL-7によって増殖や活性化を促進している。
引用:プレスリリース「固形がんに対して極めて治療効果の高い免疫機能調整型次世代キメラ抗原受容体発現T細胞『Prime CAR-T細胞』の開発」(https://www.amed.go.jp/news/release_20180306-02.htmlより)
もうひとつの今後の展開としては、他の薬剤との併用療法に関する検討も進んでいくことでしょう。最も可能性があるのはチェックポイント阻害薬との組み合わせだと考えています。例えばCD19 CAR-T細胞療法の効果がみられない場合、原因のひとつは先述したCD19の消失なのですが、それ以外にもおそらくCAR-T細胞が機能不全に陥っている可能性が考えられます。その機能不全に陥った理由としては、PD-1のようなチェックポイント分子が発現して、CAR-T細胞がPD-1のシグナルで抑え込まれているのかもしれません。そうであれば、CAR-T細胞とPD-1抗体をコンビネーションで使おうというのは当然の考え方であり、米国ではすでに臨床試験が始まっています。チェックポイント阻害薬だけでなく、抗がん剤や放射線治療との組み合わせも有効かもしれません。特に、CAR-T細胞の機能を妨げることなく、がん細胞だけを叩くような治療との併用により高い相乗効果が得られるものと思われます。
毒性をどう軽減するかという点についても、研究が進められています。CAR-T細胞療法の主要な毒性であるCRSは、つまるところ免疫が活性化されすぎたためにT細胞が過剰に増殖し、大量のサイトカインが放出されていることによるものです。それなら、そもそも体内でのCAR-T細胞の増殖をコントロールできればよいのではないか、と考えられます。この観点から、自殺遺伝子を導入することによって機能を制御する「オフスイッチ」や、低分子薬剤により活性化シグナルを誘導する「オンスイッチ」を持つCAR-T細胞の開発が進められています。これが現実のものとなれば、CAR-T細胞療法後にスイッチを切り替える薬を投与するなどの方法で、CRSなどの副作用を回避できる可能性があります。
CAR-T細胞療法をあらゆる患者さんに届ける
CAR-T細胞療法をめぐるひとつの話題として、医療費の問題が取り上げられています。米国では日本円にして1回5,000万円以上の費用がかかるとも言われており、私たちもコストの問題を考えることは避けて通れません。ただ重要なのは、高いか安いかの議論ではなく、どこにコストがかかっているのかを考えることであり、どうやってコストダウンするかということだと思います。この治療法で費用がかかるのは、他でもないCAR-T細胞の製造に関わる部分です。治療に用いる細胞には極めて高い品質が求められるため、厳密なGMP基準を満たす細胞調製施設(CPC)で、非常に慎重に細胞の培養や遺伝子操作を行う必要があります。この調製にかかるシステムと人材のコストが大きいのです。また、品質試験にも多大なコストがかかります。コスト削減にまず有効なのは機械化、自動化でしょう。今は人間が無菌状態に留意しながら行っている作業を、今後ロボットが行えるようになり、患者さんから血液を採取するところから自動的に進み、2週間後にはCAR-T細胞ができている、というようなシステムがあれば理想的です。しかしすべてを一挙に自動化することはもちろん困難ですので、まずは細胞培養のプロセスや、遺伝子組み換えの作業を機械化するための研究が行われています。
コスト削減のもうひとつの方法としては、ひとつの検体から作ることのできるCAR-T細胞の量を爆発的に増やすことです。このとき思いつくのはiPS細胞です。残念ながら現時点では、iPS細胞から機能的に優れたCAR-T細胞を大量に製造することはまだまだ難しく、長期安全性の問題もあるためハードルは高いのですが、それらの方法が技術的に確立されれば革新的な変化が起こるのではないかという期待はあります。また、他家細胞で作るというアイデアもあり、将来的にはready madeのCAR-T細胞療法という流れも考えられます。しかし、拒絶反応にどう対処するかという大きな問題に加え、ゲノム編集などのさらなる遺伝子操作技術を使用する必然性が出てくるため、そのコストや技術的課題をどうクリアするか、ということも重要です。
さらに、医療現場でどのように使ってもらうかということも課題です。新しいモダリティの治療薬は、まず使っていただく先生方に十分に理解していただくことが重要で、そのためには研究サイドからの啓発が欠かせません。「CAR-T細胞とはそもそも何か」に始まり、作用機序や副作用の現れ方、治療選択はどのように決めるのか、免疫学的なバイオマーカーはどのように見るのかなど、ハンドブックなどを作成し周知する活動も必要でしょう。例えば、私は日本臨床腫瘍学会が編集したがん免疫療法ガイドラインの作成に参加しており、臨床医の先生方とディスカッションをしながら治療プロトコールの最適化やがん免疫療法の標準化を目指した取り組みにも従事しています。今後はCAR-T細胞療法についても同様に、患者さんのためにはどう使うのが良いのかということを追求し、適切な使用方法や臨床的エビデンスを周知していくことが重要です。
自らの研究を社会実装するために
CAR-T細胞療法のような画期的な技術であっても、それを開発するだけでは十分ではなく、結果的に社会実装されなければ意味がありません。私たちは先述の通りバイオベンチャー企業と共同開発を行っており、私自身もその企業(ノイルイミューン・バイオテック株式会社)に参加しています。研究成果を社会実装にまで至らせるには長い道のりがあり、その過程でやはり資金は必要です。有効な技術がアカデミアで開発されたときに、それに呼応してベンチャー企業が立ち上がり、ベンチャー・キャピタルから資金提供がなされ、それを使用してさらに技術を最先端に進化させる、このような枠組みができれば理想的です。実際には米国ですら投資が失敗に終わることは多いのですが、それでも1つか2つでも画期的な成功例が出れば、社会への貢献は大きいはずです。実際には企業での活動は研究とは勝手が違い大変なことも多いのですが、日本でもようやく国によるベンチャー支援など体制は整ってきましたので、今後はマインドの部分や人材育成、人材の流動化なども含めた環境が育まれ、技術を社会実装できるための枠組みが成熟していくことを期待しています。
これからの若い研究者の方にも、自分の技術を社会に送り出すということを意識して研究に取り組んでもらうことを期待しています。そのためには、まずはベースとして誰にも負けない自分の専門知識を身につけることが必要です。そのうえで、海外留学や企業での勤務など多様な経験を積み、その中で一貫した自分の目標を見つけられれば自ずと道は拓けてきます。思えば免疫細胞も、自分の身体を守るという目的のもと、多様な機能を持って働いています。この意味では、人間の集団も細胞の集団も目指すところは同じなのかもしれません。
(1) N Engl J Med. 2018 Feb 1;378(5):439-448.
(2) N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):45-56.
(3) J Clin Oncol. 2018 Aug 1;36(22):2267-2280.
(4) Nat Biotechnol. 2018 Apr;36(4):346-351.
玉田 耕治 先生
【略歴】
九州大学医学部を卒業後、がん免疫学の研究にて医学博士を取得。その後米国にて 13 年間にわたり、最先端のがん免疫療法の研究と開発に従事。Mayo Clinic 免疫学にて研鑽を積み、その後 Johns Hopkins 大学にて Assistant Professor として独立。さらに、Maryland州立大学がんセンターにて、がん免疫治療プログラムの基礎研究部門リーダーを務めた。2011年より現職。
インタビューを終えて
研究業績の素晴らしさもさることながら、CAR-T細胞療法を現実の患者さんに届けるために、各地での講演や企業での活動、さらに臨床医とのネットワーキングと、労を厭わずあらゆることに取り組まれている姿勢に感銘を受けました。語り口は丁寧で穏やかなのですが、その奥に、ご自身の強い目的意識に裏付けられた静かな熱意を感じました。
インタビューア・執筆 早川威士
(ASCA Bulletin 22号 2019年5月発行より)
ASCA Bulletinとは:
アスカコーポレーションが年3回発行している広報誌です。ご興味のある方は、弊社営業部までご連絡ください。